住居表示とは
住居表示制度の目的
従来から、町名と土地の番号である地番を番地として用いることで住所の表記がされていますが、地番は必ずしも連番で並んでおらず、土地の売買等により分合筆されることで枝番号や欠番号、飛び番号が生じ、不規則な並びとなっています。
それに伴い、救急車、郵便、宅急便等が住所を基に建物にすぐに辿りつくことが出来ないようになり、生活面に支障をきたすようになりました。
このような不便をなくすため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、地番とは別に規則的に数字が並ぶように住所を付定できる住居表示制度が誕生しました。
住居表示の方法について
町を分かりやすく区切り、新しい町名を付けます。
- 町の境界は、公道、河川、水路、鉄道などの目に見えるはっきりとした恒久的なもので区切ります。
道路をもって町の境界とするときは、南北線の道路にあっては東側を、東西線の道路にあっては北側を、それぞれ境界線とします。河川をもって町の境界とするときは、河川の中心線を、鉄道の場合はその側線を境界線とします。 - 町名は、従来の名称や歴史、伝統、文化を大切にしたものにします。
- 町の名称として「丁目」を付ける場合には、都市計画道路和歌山港鳴神山口線を東西の軸、国道26号線及び国道24号線を南北の軸とし、その交点である県庁前交差点を起点として順次配列し、「丁目」の数は9丁目以下にとどめるようにし、中心点又は軸に近いほうから始め、遠い方へすすみます。
- 「宇」の呼称は用いないこととします。
街区を作り、番号をつけます。
- 街区の境界も原則として、公道、河川、水路、鉄道などの目に見えるはっきりした恒久的なもので区切ります。
- 街区符号は、数字を用い中心点(県庁前交差点)又は軸となる街路に最も近い街区を起点とし、千鳥蛇行式に順序良く配列するものとします。この場合の起点は、丁目の起点と一致させるようにします。街区符号は、数字に「番」を付けて呼ぶようにします。
住居番号を付けます。
- 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて、建物その他の工作物に付けるものとします。
- 原則として、中心点に近い街区の角を起点として、右回りに、街区の境界線を10メートルの間隔(「フロンテージ」といいます。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号を付けていきます。
- 住居番号は、各建物その他の工作物の主要な出入り口が接する基礎番号となります。
- 住居番号の呼称は、数字に「号」を付けて呼ぶようにします。
- 住居表示の表記については、下記のようになります。
(1)一般的な表記
和歌山市○○町(丁目) ○番 ○号(町名+街区符号+住居番号)
(2)部屋番号を含む表記
和歌山市○○町(丁目) ○番 ○-201号(町名+街区符号+住居番号)
※201は部屋番号
表示板を取り付けます
- 現在地や訪問先が分かるように、各街区の四隅には街区表示板を取り付け、各建物の玄関や郵便受けのそばなど、通行人から見やすい場所へ、お渡しする住居番号表示板等を取り付けていただきます。
住居表示の付定の具体例
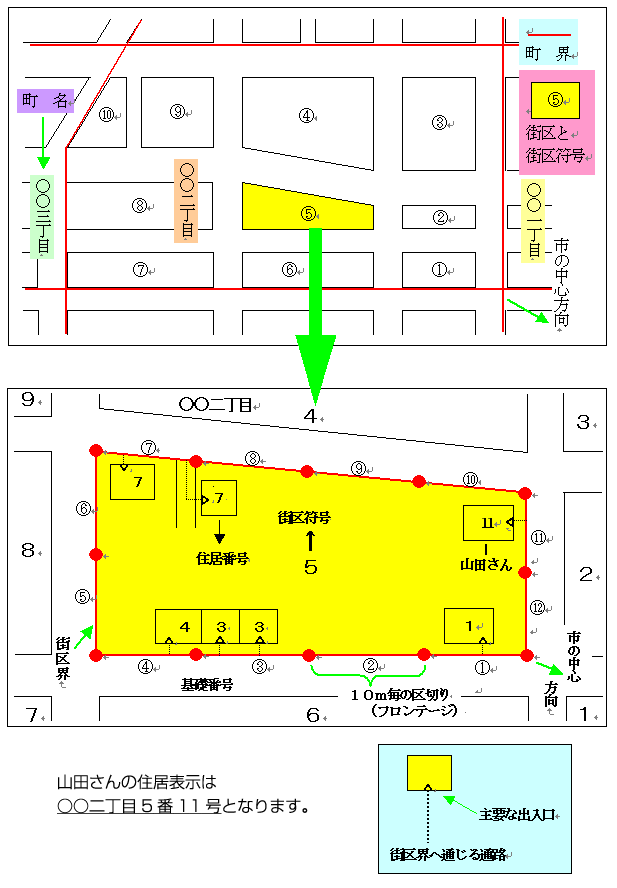
住居表示実施後に関するご案内
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
